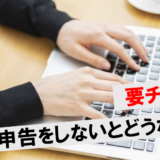「副業をしている場合の年末調整の方法を知りたい」
「手続き漏れで損したくない」
「年末調整をすると副業がバレるのではと不安」
年末調整などの副業の納税について、難しいことも多く理解しにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
年末調整をしないことで起こるデメリットや、副業がバレない方法も気になりますよね。
そこで、この記事では副業の年末調整について、解説していきます。
- 年末調整の概要
- 年末調整をしない場合のデメリット
- 副業ワーカーの年末調整方法
- 確定申告をする人、しない人の判断ポイント
- 会社に副業がバレる理由と対策
年末調整で損をしたくない方や、副業バレを防ぎたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
年末調整とは「所得税の過不足を計算する手続き」のこと。概要を説明

ここでは、年末調整の概要について、以下の3点を説明していきます。
- 年末調整の概要
- 年末調整になる人の条件4つ
- 年末調整の対象にならない人の条件7つ
それぞれ詳しく確認していきましょう。
年末調整の概要
年末調整とは、所得税などの納税額の過不足を計算する手続きのことです。
会社は従業員に支払う毎月の給与から、所得税などの税金を差し引いて納税する「源泉徴収」を行います。
毎月源泉徴収した税金の1年間の合計額は、給与を支払われる人の本来の納税額と、差があるのが一般的です。
源泉徴収は基本的に報酬の10.21%が原則ですが、所得税の税率区分は年収に応じて5%~45%で計算されます。
すると10.21%では払いすぎている人も出てきてしまうため、年末調整で過不足を計算するのです。
1年間の給与総額を確定させるために、年末に調整を行います。
年末調整の対象になる人の条件4つ
年末調整は、すべての人がおこなうものではなく、条件に当てはまる人のみがおこないます。
対象となるのは、以下の4つの条件のいずれかに当てはまる人です。(参考:国税庁 年末調整の仕方)
- 1年を通じて、勤務している人。
- 年の途中で就職し、年末まで勤務している人。
- 年の途中で退職した人のうち、以下に当てはまる人。
-死亡により退職した人。
-身心の障害のため退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人。
-12月中の給与の支払を受けた後に退職した人。
-パートタイマーとして働いている人が退職した場合で、給与の総額が103万円以下である人。 - 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非住居者となった人。
ほぼすべての方が「1年を通じて勤務している人」に当てはまるため、年末調整を行う必要があります。
年末調整の対象にならない人の条件7つ
年末調整の対象とならないのは、以下の7つのいずれかに該当する人です。(参考:国税庁 年末調整の仕方)
| No. | 条件 |
| 1. | 年間の給与収入額が、2,000万円を超える人 |
| 2. | 災害の被害を受けて「災害被害者に対する租税の免税、徴収猶予等に関する法律」の規定により、所得税などの納税猶予や、還付を受けている人 |
| 3. | 2ケ所以上から給与の支払を受けている人で、いずれか1つの会社に扶養控除等(異動)申告書を提出している人 |
| 4. | 年末調整を行うときまでに、扶養控除等(異動)申告書を提出していない |
| 5. | 年の途中で退職した人で、「対象になる人」のNo.3に該当しない人 |
| 6. | 非住居者 |
| 7. | 継続して同一の雇用主に雇用されない、日雇い労働者など |
年末調整をしないと納税額が高くなるのがデメリット

年末調整をおこなわないと、納税額が高くなってしまう場合があります。
理由は「各種控除の申告」が、受けられなくなるからです。控除を受けられないことで、自身の総所得額が多くなってしまうため、支払う税金額も高くなります。
支払わなくてもよい税金を払うことになるため、損をしてしまいます。年末調整をおこない、しっかりと各種控除の申請をしましょう。
副業をしている人が年末調整ですべきこと2STEP

ここでは、副業をしている人が年末調整の時期にすべきことを2つ解説していきます。
- 本業では「年末調整」をおこなう
- 副業では所得20万円以上で「確定申告」をおこなう
1. 本業では「年末調整」をおこなう
本業では会社で配布される書類に必要事項を記載し、提出します。
なお複数の場所から給与所得がある場合は、収入が多い会社を本業として、年末調整を行います。
配布される必要書類は、以下の通りです。
【必要書類】
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得の住宅借入金等特別控除申請書(対象者のみ)
年末調整の時に申請できる控除があり、その書類も用意する場合があります。
【控除のために必要な書類】
- 個人型確定拠出年金の掛金を証明する書類
- 生命保険料控除証明のためのハガキやデータ
- 地震保険料控除証明のためのハガキやデータ
- 控除していない社会保険料を証明する書類
- 配偶者特別控除に必要な収入証明
- 住宅ローン控除に必要な住宅借入金等特別控除申告書、借入金の年末残高等証明書
2. 副業では所得20万円以上で「確定申告」をおこなう
副業では、所得20万円以上で「確定申告」をおこなう必要があります。
そもそも「年末調整」と「確定申告」の違いは、手続きをおこなう人が違うところにあります。
- 年末調整は、会社が雇用者の納税額を決定するためにおこなう手続き
- 確定申告は、個人が税額を計算し、納税をおこなう手続き
会社で年末調整を行わない仕事に関しては、すべて副業として扱われます。
副業年収が20万円を超えていたら、確定申告を行う必要があると考えておきましょう。
確定申告の具体的な方法は、以下の記事をご確認ください。
>>【初めてでもできる】フリーランスの確定申告のやり方5ステップ!手続きが不要なケースや必要書類も解説
副業で確定申告を「する or しない」?判断するポイント2つ

こちらでは副業ワーカーが、確定申告をする場合としない場合の判断ポイントを、2つ紹介します。
1. 副業では、「20万円以上」で確定申告が必要
2. 20万以下の人は「控除」と「住民税」を確認
ぜひ、参考にしてください。
1. 副業所得が「20万円以上」の場合は確定申告が必要
結論として、副業の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
ここでは、年末調整を受けた本業以外の仕事を「副業」としています。
副業といえば、短期のアルバイトなどを思いつきがちですが、以下のようなものも含まれます。
- ホームページの作成や、ベビーシッターなどの役務の提供による所得
- 暗号通貨の売却等による所得
- 競馬などの公営競技の払戻金による所得
注意すべきなのは、収入が20万円以上であっても、経費を引いた際に20万円以下になる場合です。この場合は、確定申告をおこないません。
確定申告は面倒な作業で負担も増えるので、所得が20万円を超えないようにすつのもひとつの手です。
所得を減らすためには、経費にできる要素を増やすことが大切です。例えば、オンラインサロンのように自己投資を増やせば、所得金額を減らせます。
詳しくは以下の記事をご確認ください
>>【事業者必見】オンラインサロンの会費は経費計上可能!種類と方法について徹底解説
2. 20万以下の人は「控除」と「住民税」を確認
20万円以下の場合でも、以下のような「控除」を受けている方は、確定申告の対象になるのでご注意ください。
| 種類 | 詳細 |
| 医療費控除 | ・保険金で補填した費用をのぞく、医療費が10万円を超える場合 ・OTC医薬品の購入費が、12,000円を超える場合 |
| 寄付金控除 | ・国や地方公共団体への寄付 ・ふるさと納税 ・特定公益増進法人などへの寄付 |
| 雑損控除 | ・災害 ・盗難 ・横領 |
また、所得が20万円以下は確定申告こそ不要ではありますが、住民税を申告する必要があります。
確定申告は基本的に所得税を申告する手続きであって、住民税は20万円以下でも支払う必要があるからです。
住民税は、年末調整や確定申告で計算された所得によって決定します。
しかし所得20万円以下で確定申告をおこなわない場合は、住民税が計算できません。
住民税申告書をお住まいの地域で取得し、自治体のルールに沿って提出してください。
なお確定申告を行えば住民税は自動的に計算されるため、面倒であれば20万円以下でも確定申告を行うことがおすすめです。
年末調整で副業は会社にバレる?理由と対策方法

こちらでは、年末調整によって副業がバレる理由とバレない対策方法を説明していきます。
- バレる理由は「翌年の住民税の源泉徴収額が増えるから」
- バレない方法は「普通徴収」をする
- バレたらトラブルに⁉「就業規則」をチェックすること忘れずに
ぜひ、ご覧ください。
バレる理由は「翌年の住民税の源泉徴収額が増えるから」
副業がバレる理由は「翌年の住民税の徴収額」が、増えるからです。
年末調整や確定申告で翌年の住民税額が決定しますが、本業だけの収入だけでなく、副業の収入を含む住民税の金額が上乗せされます。
本業の会社で計算した額よりも徴収額が増えることになり、担当者に副業がバレる確率は高いでしょう。
バレない方法は「普通徴収」をする
副業がバレないためには、住民税を「普通徴収」にするとよいでしょう。
一般的には、住民税の額は本業の会社に通知されます。
一方で普通徴収にすれば、住民税を自分自身で納付できるので、会社への通知を避けられます。
バレたらトラブルに⁉「就業規則」をチェックすること忘れずに
厚生労働省でも副業は推奨されていますが、副業を禁止している会社も多くあります。
就業規則によっては懲戒解雇などの重大なペナルティを課されるリスクがあるため、本業の会社が、どのような就業規則になっているのかを事前に確認しましょう。
本業との兼ね合いを考えたうえで、副業にチャレンジすることがおすすめです。
2,480円で10種類以上のビジネスを学べる「人生逃げ切りサロン」
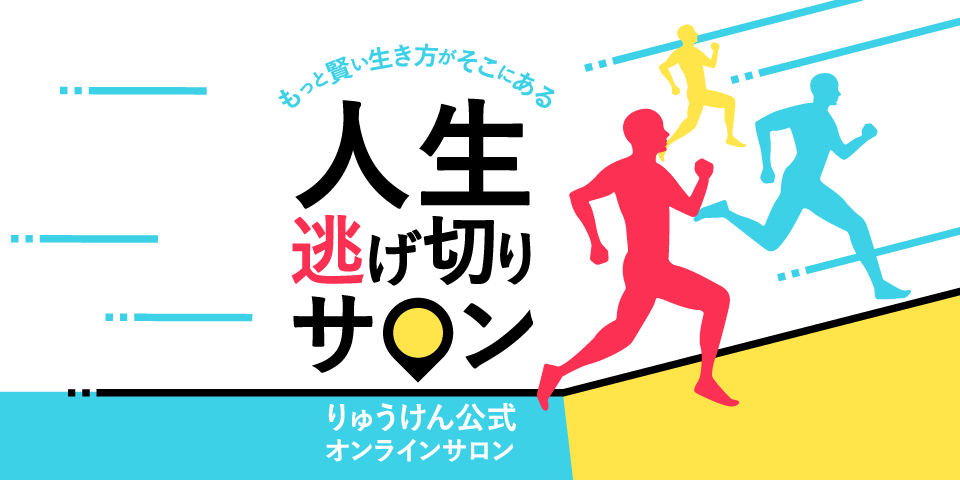
人生逃げ切りサロンは、約5,000名のメンバーが所属している、フリーランス系のオンラインサロンです。
- プログラミング
- 動画編集
- Webデザイン
- ライティング
- ネット物販
など、各界の実力者が集結し、オンライン講座を管理しています。
所属しているだけでプログラミングや動画編集の講座を受講できたり、ビジネスで成功を収めている人と交流できたりと、数多くの特典が魅力です。
参加料金は月額2,480円もしくは年額26,400円とリーズナブルなので、これから「将来を考えてビジネスを始めたい」という方にピッタリ。
ビジネススキルを身につけて、人生を逃げ切りたいと考えている方は、ぜひ加入をご検討ください!